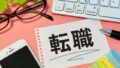大学院に入ってからはとにかく数学をたくさん使用するようになり、勉強している息子です。数学の勉強が楽しくて、なぜ今までこんなに楽しい学問が苦手だったのだろうと言っている程です。
大学院から専攻を変更して勉強すると言い出したときは、驚きました。数学がそんなに得意ではなかった息子が数学をたくさん勉強する分野に行くわけですから、院試も大丈夫なのかと心配しました。
小さい頃からずっと息子の勉強を見守ってきました。中学に入るまでは私が付きっきりで勉強を教えていました。算数ができないわけではないけれど、特別センスがあるわけでもなく、普通といった感じでした。積み重ねの学問なので、とにかく基礎を大事にして、転ばないようにだけは気を配っていました。中学に入ってからも見守っていたつもりでした。ところが中学からは厳しい運動部の部活に入部したせいもあり、疲れて勉強できない日々が続き、気が付いたら数学がほとんどできない状態になってしまいました。ある日、
「因数分解がわからない」
と息子が言い出しました。中2の終わりごろだったと記憶しています。学習に問題がないと思っていただけにひっくり返りそうになりました。
確かに担任の先生からは「数学がちょっと・・・」とは聞いていたのですが、まさかそこまで落ちているとは予想外でした。「塾に通う?」とアドバイスをするものの、「部活ができなくなるから嫌だ」と拒否されてしまい、反抗期真っ只中ということもあり、私の意見は全く聞いてくれませんでした。
そして中3になり、部活を引退し、いよいよ高校入試が目前に迫り、模試の結果などから、自分がかなりまずい状況になっていることに気づいた息子。特に数学が壊滅的で足を引っ張っていることに愕然とし
「塾に通わせてください」
え?と息子は事の重大さに気づき、私に頭を下げてきました。
こんな時期に?!受験日まで3か月もありませんでした。家庭教師をつけるかどうかも考えましたが、それはお金がかかりすぎると、息子が私に遠慮し受け付けませんでした。その代わり個別指導の塾を息子が自ら探し出してきて、入塾しました。1か月過ぎたころ、「なんか先生の教え方があんまり良くなくて意味がないし、勉強の仕方がわかってきたからやめる」と言い、結局塾は1か月半ほどでやめて独学で勉強をし始めました。
結局、第一希望の高校ではないものの、第二志望の高校に合格し、春休みに入ったころ、息子は再度私に頭を下げて「高校からは数学だけでいいので塾に通わせてください」と言ったのでした。数学に関してはあんな思いをしたくないと大分後悔の念があったらしく、春休みの間にあちこちの塾を見学して廻り、自分で塾を決めてきたようなのです。
「絶対に2次関数だけは、落とすな。しっかり勉強しとけ。」
入塾見学時の先生のこのアドバイスが息子を数学を少しづつ得意にしたのでした。
高校に入学してからというもの、因数分解が解けなかった息子とは思えないくらい、めきめきと数学の成績を伸ばしていきました。しかし数学が大好き、大得意というわけではなかったので、結局、大学での専門は数学をそんなに使わなくとも良い化学の道に進みました。
ところが、「これからの時代は化学の知識だけではだめだ。学際が必要な時代だ。」とAIの勉強の道に転向した息子。院試の受験勉強では独学で数学を必死に勉強していました。
そして今、大学院では数学を駆使し研究をしているわけですが、「本質を知れば知るほど、数学は楽しい学問だということが分かった。自分がこんな風になるとは思わなかった。」と本人が一番驚いていました。
そして今は自分の後輩に伝えていることがあるそうです。
子供の頃や中学・高校程度の得意不得意はあまりあてにはならない、人間はどこに可能性を秘めているかはわからない。いつどこで能力を発揮するかなんてわからないから、決めつけてはいけない。だから視野を広げて色んなことにチャレンジして、自分の引き出しをたくさん作るといい。
ちなみ数学の本質は何か?どうして数学を勉強することが楽しいと思えるようになったのかというと、数学の問題を取り組むときに、「なぜこうなっているんだろう?」という視点で考えるようになったら、すーーーーーと数学の本質がわかるようになり、楽しくなってきたとのこと。
私のパートナーのEさんも数学が大好きで、大学・大学院では物理の専攻(大学の物理というのは、ほぼ数学でできています。)でした。彼も同じことを言っていました。高校1年生まではあまり成績が良くなかった数学だったけれど、ある日突然わかるようになったそうです。それがやはり息子が言っていたのと同じように「なぜこうなっているんだろう?」と数学的思考で考えるようになってからだったとのことです。
数学は公式や解き方を覚えたり、練習するものではなく、「どうしてこういう考え方になるのだろう。」「なぜこの公式が必要なのだろう。」という原理原則を考えることによって、楽しさが理解できる学問なのだそうです。
この数学的思考は数学という学問をするだけではなく、社会を生きていくうえでも必要な思考だと感じます。特にこれからはAI時代に突入する高度な情報化社会になります。発信される情報の信ぴょう性の見極め、またどのようにAIを活用していき、人間はどのようにAIと共存していくのかを考えるための根本的思考になるのではないでしょうか?